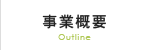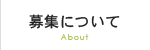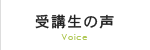活動報告
「先取り!科学者の体験」第1回講座
| 実施日 | 2012年6月17日(日)13:30~16:00 |
| 場 所 | 理学部C303講義室 |
| テーマ | 絶対零度への挑戦(温度とエネルギーについて) |
| 概 要 | どのようにしたら低温を得ることができるか。温度とは何か。絶対零度への足跡と、冷蔵庫やヒートポンプなど熱エネルギーの変換の原理の話と、断熱圧縮あるいは液体窒素を使った実験で熱エネルギーの変換原理を学ぶ。 |
| 講師など | 土屋良海理学部名誉教授、TA無し |
| 受講生等 出席状況 |
今年度の受講生は25名で構成。受講生25名中24名が出席、参加保護者:23名 |
| 受講状況 | ■受講生課題レポート(提出数24/参加人数24) ■受講生生アンケート(提出数24/参加人数24) ■保護者アンケート(提出数21/参加家族数23) |
| 講師所感 | 小学生がほとんどの参加者に対して選定したテーマが少し難しかったことと、いくつかの簡単な演示を行いそれに対して参加者のアイデアを問いながら話を進め、最後に少し難しいまとめを行う等の工夫が必要であったと反省しております。パワーポイントのスライドのコピーを配布資料としましたが、デモ実験の要旨とねらい等を加えて講義を聞かなくとも小学生が読んでテーマの概要がわかるような平易なテキストを作製する必要を感じました。この企画に参加したことが、みなさんの自然の原理(科学)を考える第一歩となることを期待しています。 |
 |
 |
| 受講生初めての講義。本人も親もやや緊張していた。 受講生:温度とはなにかということを考えたことがなかったのですごくしんせんに感じました。 |
低温の物理の歴史の説明。小学生には初めて聞く物理学者の名前が多かったようだ。 保護者:冷蔵庫、エコキュー、クーラーとなど身近なものについて、知ることができて興味を持ちました。もっと知りたいという気持ちになりました。 |
 |
 |
| 土屋講師による風船内の空気の液化実験。 保護者:(物理を身近に感ずるようになった活動は:)バラや輪ゴム等認識している部室の性質が「温度」によって全く異なる性質の物体になる現象を見て、(子供は)興味を持てたと思う。 |
サーモグラフィーの画面。 受講生:サーモグラフィーをみれてよかった 受講生:(おもしろかったことは)サーモグラフィーで自分の体温をはかるところ。 |
(写真の下のコメントは、受講者アンケートから転載)