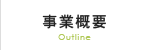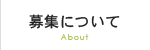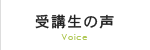活動報告
ホーム>活動報告 - 【ステップ】科学基礎講座
平成23年度活動報告
生体内たんぱく質の分離実験
| 実施日 | 2011年9月3日(土)10:00~15:30 |
| 場 所 | 新潟大学理学部講義室・実験室 |
| 概 要 | 生体内には多くのたんぱく質が含まれるが、これらをSDSゲル電気泳動により分離する手法を学びます。実験材料としてリボソームや各種酵素などを用います。 |
| 参加者 | 高校生4名 |
| 講 師 | 理学部 内海利男教授 伊東孝祐助教 |
| 内海先生の講義が初めにありました。 受講者の声:たんぱく質の合成とかつくりとか、今までイマイチよく分からなかった。実験をしながら、こういうことに注意する必要があるとか、実験をする心構えやこころがけなどが少しわかったのがよかった。 |
 |
| 実験風景 受講者の声:・実験で、今まで触れたことのない器具をつかえるところがいい。 ・学校の実験はほとんどなかったけど、やはり実験しなければわからないことも多いなあと感じた。 |
 |
|
受講者の声:実験の内容から派生させて、他の分野のことについて聞いたりすることができたので、より深められた。 ・もっと多くの人が参加すべき価値のあるものだと思った。 |
 |
| この日の講座では例えば、次のようなレポート課題が出されました。 受講者の声:・精製たんぱく質(EF-1)の電気泳動の移動度より分子量を推定せよ(グラフに推定根拠も示せ) ・EF-1はおおよそ何個のアミノ酸が連結した分子か …その他 電気泳動の結果は ゲル電気泳動の結果ファイルへ ゲル電気泳動のパターン |
 |
放射線と現代医療
| 実施日 | 2011年9月24日(土)10:00~15:30 |
| 場 所 | 新潟大学理学部実験室 |
| 概 要 | 放射線はただ見えなくて怖いものだけではありません。実は身の回りの隠れたところで大活躍しています。放射線の性質から最新の医療への応用までを紹介しました。 |
| 参加者 | 高校生4名 |
| 講 師 | 理学部 大坪 隆 准教授 |
| 受講生に 対する感想 |
講義及び実験の構成であったが、皆まじめに取り組み、データ解析も共同で行えた。レ提出されたポートについては基本的なところを押さえてくれており、十分なものと考えている。 |
| 受講者の声:少し難しく感じたが、普段言葉を聞く割にあいまいな内容だったため、面白いと思った。昔、原子は不変なものだと思われたが、実際にはそうでないことや原子でのエネルギーの変化によって光を放ったりすることなどが興味深いと思った。 |
| 受講者の声:放射線については、中学生の時から興味を持っていたので、今回の講座はとても勉強になった。しかし、実験はやはり難しいと思った。来年からは物理を勉強するので少し先取りができて、良い経験となった。 |
| 受講者の声:最近話題になっている放射線のことが学べてとてもためになった。医療等にも使われているが、やはり放射線は恐ろしいものだと感じた。人体からも放射線がでているということは初めて知ったので驚いたのと同時にそこまで過敏に考えなくてもいいのかもしれないと少し思った。 |
| 受講者の声:放射線について、順を追ってわかりやすく説明してもらったので放射線について理解を深めることができてよかった。放射線の医学への利用についても、ここまで進んでいることが分かって、新しい発見が多かった。放射線がどういうものか今まで以上鮮明なイメージが持てるようになった。大学についての話を聞けたのもよかった。 |
| 受講者の声:対消滅のγ線は反対方向に出るのを確かめる実験で予想と異なる結果が出たり、自然放射線量が以外と多いことに驚いた。また、講義中だけでなく休み時間にも大学の話など聞けてよかった。 |
サーモクロミック錯体を作ろう
| 実施日 | 2011年10月15日(土)10:00~15:30 |
| 場 所 | 新潟大学 総合研究棟(物質・生産系)実験室 |
| 概 要 | 温度を変えると色が変化する現象(サーモクロミズム)を示す金属錯対体を合成し、変色の様子を観察します。固体のまま、溶液にしたとき変色する錯体など、変色の理由を考えます。 ■午前中:錯体の基礎知識、錯体の応用、午後行う実験の説明など ■午後:錯体の合成、サーモクロミズムの観察、吸収スペクトルの測定、まとめ |
| 参加者 | 高校生3名 |
| 講 師 | 理学部 佐藤敬一准教授 |
| 女性研究者として活躍中の小林みどりさんの講義が初めにありました。 |  |
| 実験風景 受講者の声:温度によって物質の色が変わって驚いた。また、実験のやり方や試薬や器具の取扱い方も学べてためになった。学校の課題研究でも似たような実験をするので今日の経験を生かしたい。 |
 |
|
受講者の声:・いろんな物質に触れることができた。初めて聞くような単語が多く、錯体も初めて学んだのでかなり難しかったが、色の変化ははっきりとしていて分かりやすかった。今日の講座で学んだことを生かし、今後の学習に励もうと思う。 ・錯体の仕組みなど、高校では習わないような事を知ることができておもしろかった。 |
 |
磁石を使ってルート図を作る
| 実施日 | 2011年11月19日(土)10:00~15:30 |
| 場 所 | 新潟大学理学部講義室・理学部構内 |
| 概 要 | 磁石・歩測を使って大学構内の道路地図を作りました。 |
| 参加者 | 高校生4名 |
| 講 師 | 理学部 豊島剛志教授 |
| この日は朝から雨で、屋外での実習は寒くもあり雨の中で大変でした。午後から、午前中に得られたデータをもとに屋内で地図を作る作業をしました。 受講者の声:「ルート図作りは難しかった。伊能忠敬は歩数で測る訓練をしたと聞いたことがある。それなりに慣れないと難しかった。また雨が降っていたのがつらかった。」 |
 |
| 午後は初めに理学部内のサイエンスミュージアムで研修を受けました。TAの人が丁寧に受講生の質問に答えてくれます。ミュージアム内にはたくさんの地質関係の資料が整理され並んでいます。 受講者の声:「サイエンスミュージアムを見せてもらって多くのことが分かった。」 |
 |
| 受講者の声:「地学の話で、実験って何をするんだろう?と思っていたけど、やってみてナットした。歩いて方角と距離を測って、何が分かるかのか?分かることは少ないだろうと思っていたが、予想以上に新しい発見や、大きなスケールのことが分かったので、地味な作業をしっかりやったかいがあった。ためになる講座でした。」 |  |
| 「ルート図作製の実習は,あいにくの雨天での実施となったが,全員一生懸命に取り組み,初めてにしては良くできたと評価される。室内の講義では,北半球と南半球で逆向きの伏角があることや内核が固体で外核が液体の鉄であること,地球磁場の成因や変化などについて,特に強い興味を持ったようである。授業の終わりには,かなり高度な内容の質問もいくつか出された。「科学基礎講座」では,実際に実験や実習を行って得たデータから考える授業は有効である。」 | |
理系進学のすすめ
| 実施日 | 2011年12月24日(土)10:00~10:45 |
| 場 所 | 新潟大学理学部講義室 |
| 概 要 | 理系の分野で、女性の研究者として第一線で活躍中の方の体験談を参考に、受講者の進路選択に役立ててもらうための講義です。 |
| 参加者 | 高校生7名 |
| 講 師 | 理学部 林八寿子 准教授 |
| この講演は、ステップ2、ステップ3の受講生全員が受講しました。 話の後の質疑では、女子高校生の積極的な質問が出ました。 |  |
無限も数えてみよう
| 実施日 | 2011年12月24日(土)11:00~15:30 |
| 場 所 | 新潟大学理学部講義室 |
| 概 要 | 個数の本質を見極めて無限個のものを数える「集合の濃度」をテーマにした講義 |
| 参加者 | 高校生6名 |
| 講 師 | 理学部 羽鳥理教授 |
| 受講者の声:「普段学校の数学でやらないような刺激的な内容だった。 無限の数について知識が深まったし、自然数と整数の個数が同じというのには驚いた。面白い内容で他の事にも応用できそうだと思う。」 | 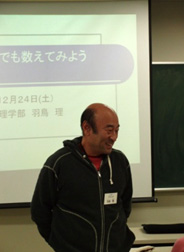 |
| 受講者の声:「今までに見たことのない数式や記号がたくさん出てきて少し難しかったですが、授業が終わった頃には少しですが理解できた気がして嬉しかったです。」集合は苦手分野でしたが、今回の授業はなんだか楽しかったです。 |  |
「目指そう未来の科学者」研究発表会
| 実施日 | 2012年3月4日(日)10:30~14:50 |
| 場 所 | 新潟市 朱鷺メッセ303小会議室 |
| 概 要 | 個数の本質を見極めて無限個のものを数える「集合の濃度」をテーマにした講義 |
| 参加者 | 40名あまり 発表者(7名の受講生全員)のほか、課題研究の指導教員、TA、保護者、受講生の出身高校の教員、一般の高校の教員、ステップ1の受講者、その他 |
| 初めに谷本理学部長のあいさつがありました。 |  |
| その後、次々と課題研究の口頭発表が行われました。 発表は12分間でその後3分間の質疑の時間があります。 写真のような、大きなデモ用のグッズ持参の発表者もいました。 |  |
| 開始前に何回も練習する姿が見られました。 |  |
| 発表の審査は、高校の先生や理学部長が行いました。審査員や会場に人から様々な質問が出ます。うまく乗り切るのもプレゼン技術のひとつです。 | 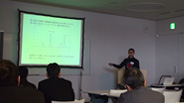 |
| 口頭発表の後はポスター発表です。口頭発表のとき以上に細かいディスカッションが行われます。 |  |
| かなり突っ込んだ質問を受けているのでしょうか… |  |
| 左の二人の小学生は、ステップ1の受講者です。案内チラシを見て、保護者と一緒に会場に来ました。何か一生懸命発表者に質問していますが、発表者はどのような質問もさばくことが求められます。 |  |
| ディスカッションは、科学者の研究にとってたくさんの収穫をもたらします。重要な機会です。 |  |
| 竹内副学部長より、ねぎらいとさらに受講者の将来に期待をするとお話がありました。 |  |
| 最後に、受講者と課題研究の指導を担当された先生との記念写真の撮影が行われました。緊張が解けて、笑顔がさわやかです。 |  |