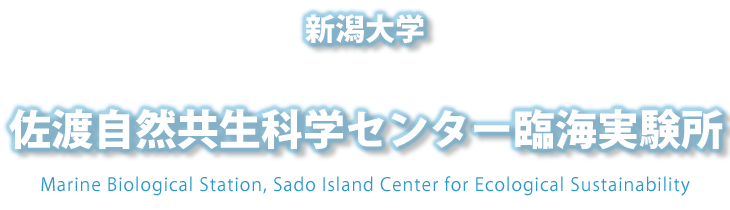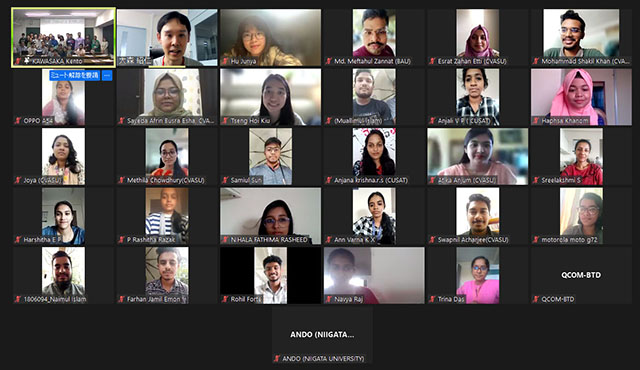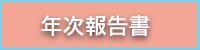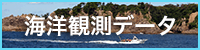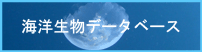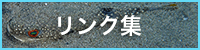2024年度 臨海実験所における講義、実習の予定
新潟大学佐渡自然共生科学センター臨海実験所は、新潟大学の学生向けの講義、実習の他に、教育関係共同利用拠点として、全国の国公私立大学の実習を受け入れています。また、小中高校や専門学校などの実習の受け入れも行っています。実習の開催をご希望の方は、臨海実験所までお問い合わせください。2024年度の実習等の日程表は以下のとおりです。
2024年度の講義、実習等の日程表
実習(一般、他大学向け)
(2024年4月15日 updated)
他大学対象公開臨海実習
公開臨海実習についての詳細はこちら
期間:2024年8月19日(月)~24日(土) (5泊6日)
シラバス、2023年度の実習についてのブログ
期間:2024年9月9日(月)~14日(土) (5泊6日)
シラバス、2023年度の実習についてのブログ
期間:2024年9月21日(月)~25日(金) (4泊5日)
シラバス、2023年度の実習についてのReport (English:PDF, 1.7MB)
期間:2025年3月3日(月)~7日(金) (4泊5日)
シラバス、2023年度の実習についてのブログ
実習(新潟大学の学生向け)
(2024年4月15日 updated)
- 【系統動物学】 (対象:理学部・農学部2年生など)
2024年7月8日(月)~11日(木)
シラバス
申込締切:2024年6月7日(金)までに学務情報システムより登録
※ 両津港から臨海実験所までは往路、復路ともに送迎バスを用意しますので、島内の交通費は不要です。
- 【理学基礎演習(フィールド科学人材育成プログラム)】 (対象:理学部理学科1年生など)
2024年7月20日(土)~21日(日) (1泊2日)
シラバス
※ 両津港から臨海実験所までは往路、復路ともに共用車および送迎バスを用意しますので、島内の交通費は不要です。
- 【臨海実習Ⅰ】 (対象:理学部生物学プログラム3年生、理学部・農学部フィールド科学人材育成プログラム3年生)
2024年8月19日(月)~24日(土) (5泊6日)
シラバス
申込締切:2024年7月5日(金)までに学務情報システムより登録
※ 本実習は、理学部自然環境科学プログラム向けの「環境生物学野外実習B」、および、他大学向けの公開臨海実習「佐渡・海洋生物学コース」と合同で開催します。また、両津港から臨海実験所までは往路、復路ともに送迎バスを用意しますので、島内の交通費は不要です。
- 【個性化科目 森・里・海フィールド実習】 (対象:全学部生)
2024年9月9日(月)~14日(土) (5泊6日)
シラバス
申込締切:2024年7月12日(金)までに学務情報システムより登録
※ 本実習は、他大学向けの公開臨海実習「佐渡・森里海の連携学コース」と合同で開催します。また、両津港から臨海実験所までは往路、復路ともに共用車および送迎バスを用意しますので、島内の交通費は不要です。
- 【個性化科目 佐渡自然共生国際実習(国際臨海実習)】 (対象:全学部生)
2024年9月21日(月)~25日(金) (4泊5日)
シラバス
申込締切:2024年5月17日(金)までに学務情報システムより登録
※ 本実習は、他大学向けの公開臨海実習「佐渡・国際臨海実習コース」と合同で開催します。また、両津港から臨海実験所までは往路、復路ともに共用車および送迎バスを用意しますので、島内の交通費は不要です。
- 【環境生物学野外実習C】 (対象:全学部1-3年生)
2025年3月3日(月)~7日(金) (4泊5日)
シラバス
申込締切:2025年1月31日(金)までに学務情報システムより登録
※ 本実習は、他大学向けの公開臨海実習「佐渡・発生/行動学コース」と合同で開催します。また、 両津港から臨海実験所までは往路、復路ともに送迎バスを用意しますので、島内の交通費は不要です。
過去の講義・実習の日程一覧へ